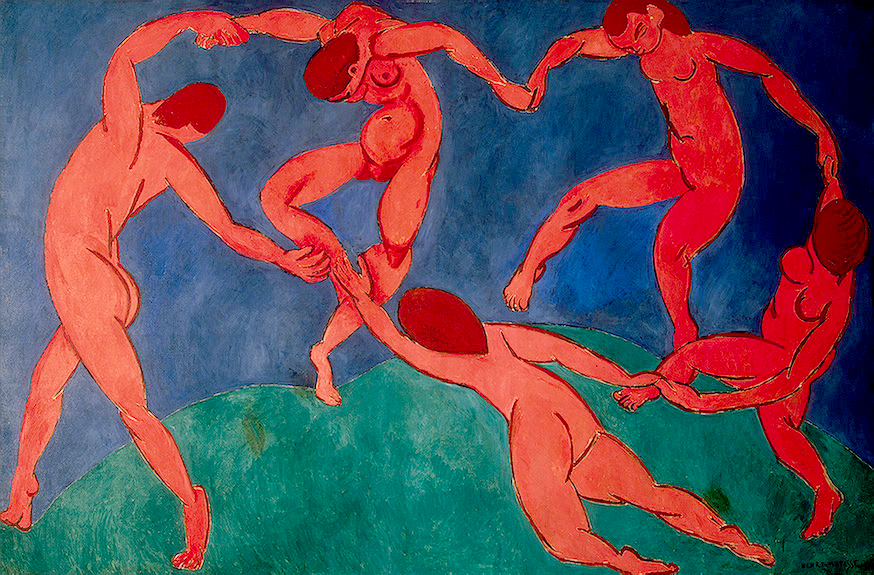ピアノを伴う一大交響曲

ブラームスは交響曲の作曲には、とても慎重だったといわれています。
なにしろ交響曲第1番の着想から発表までに要した期間が20年というのですから、ちょっと尋常ではありませんよね……。
もちろん、それはベートーヴェンの交響曲という大きな存在があったからですが、協奏曲の作曲に関しても軽々しく作曲するということはなかったようです。
ピアノ協奏曲第2番の場合も同じです。徹底的に推敲を重ねて生み出された作品なので、充実度は抜群ですし、どこをとっても薄味なところはありません。
ブラームスのピアノ協奏曲第2番変ロ長調は、それまでのソロ楽器が活躍するテクニカルで華やかな協奏曲とは性格がちょっと違います。
この協奏曲はまるで交響曲のようにあらゆるパートが雄大で充実しています。ピアノ中心の協奏曲ではなく、ピアノ独奏を伴う交響曲といっても過言ではないでしょう。
時に「煮ても焼いても食えない」とか、「重厚すぎる」という批判を浴びることもありますが、こんなに楽想が豊かで変化に富んだ作品も滅多にないでしょう。

演奏の難しい協奏曲

この作品は決して超絶技巧を売りにした作品ではありません。にもかかわらず、ピアニストの間では最も弾きこなすのが難しい曲とさえ言われています。
とにかく集中力の持続が難しい曲で、ピアノの即興的な自在感は半端ありません。
それでいて「カッチリ弾けました」のような技巧的な演奏は受けつけないという……、ともかく難しい曲なのです。
ですからピアニストと指揮者、オーケストラの息がピッタリ合い、白熱した渾身の演奏が繰り広げられると、途轍もない感動を受けたりするのです。
各楽章の聴きどころ
第1楽章 Allegro non troppo
第1楽章は出だしの朗々としたホルンの響きが、何ともいえない郷愁を奏でてますね。その後、木管楽器や弦楽器が絡むと、朝焼けの広大な情景が眼前に浮かんでくるようです。
雰囲気満点の中、曲は展開部、再現部にかけて大きな盛り上がりを見せます!
第2楽章 Allegro appassionato
第2楽章スケルツォは彫りの深い響きが連続して現れます。
金管とピアノ、弦楽器が一体となって織りなす立体的な構築はいかにもブラームスらしく、起伏の激しい嘆きの歌が痛切に心に刻まれます。
第4楽章 Allegretto grazioso – un poco piu presto
フィナーレの第4楽章ロンドは、ブラームスとしては異例の愉しく明るい舞曲になっています。肩の力を抜いた気の利いた曲調が何とも意地らしく、微笑みを浮かべながら曲は幕を閉じていくのです。
万感の想いが込められた第3楽章

第3楽章アンダンテは第1、第2楽章のシンフォニックな曲調とは明らかに違います。
このアンダンテは本当に何度聴いても飽きません。音楽がよく出来ているし、とにかく普遍的な意味で美しいのです。
特に万感の想いが込められたチェロの主旋律が印象的です。しかも、このチェロの響きには優しさや愁いの心が溢れているのです。
これに華を添えるように管楽器が加わると、走馬灯のように様々な情景が浮かんでは消えていくように感じますね……。
第3楽章 Andante
ブラームスは協奏曲でも、主役の独奏楽器を脇役に据えてみたり、オーケストラの一部として扱ったりもします。
それが功を奏しているのが第3楽章でしょう。
この楽章のピアノは決して出しゃばったりしません。あくまでも詩的なモノローグのように、揺れ動く心を伴奏を伴いながら綴っていくのです。
ピアノの調子が変化すると、それをサポートする伴奏の色合いも変化し、情景が変化していくことに気づかされます。
最後はチェロの主題と重ね合わせるようにピアノが鳴り響くのですが、まるで人生の一ページを覗くような趣さえありますね…。
この楽章を聴くと、ブラームスは正真正銘の音楽詩人であることがよく伝わってきます!

バックハウスの唯一無二の名演奏
この曲には理想の名演奏があります。
それがバックハウスのピアノ、ベーム指揮ウイーンフィルの演奏(ユニバーサルミュージック)です。
バックハウスのピアノは、音と戯れるようなまったく自在な境地で弾いてることに驚かされます。
つまりテクニカルな冴えが鼻につくことは皆無で、この音楽の本質を体現し、音楽の化身となっているといってもいいでしょう!
強弱やリズム、フレーズの間も違和感がなく、紡ぎ出される音はブラームスの心情をその如くに表しているかのようです。
ベーム指揮ウイーンフィルの演奏もバックハウスとの息がピッタリ! 本質をズバリ突いていて見事と言うしかありません。まさにピアノ、指揮、オーケストラ、録音まで揃った極上の名演奏です!
1967年のデッカ録音ですから、すでに半世紀の年月が経っています。それにもかかわらず、今でもみずみずしい響きが美しく、楽器の音もバランスが良く、そこかしこから臨場感が伝わってきます!