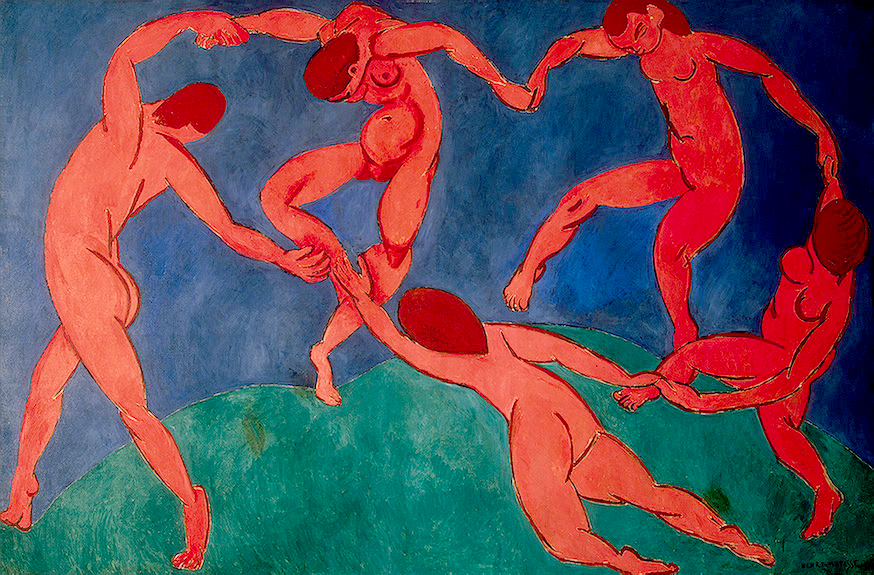以前からクラシック音楽は「ヒーリング効果がある」とか、「お腹の赤ちゃんが子守唄のように聴いている」とかいろいろな噂があたかも本当のように伝えられてきました。
以前からクラシック音楽は「ヒーリング効果がある」とか、「お腹の赤ちゃんが子守唄のように聴いている」とかいろいろな噂があたかも本当のように伝えられてきました。
でも何の根拠があってそんなことが言われているのか? 不思議に思われる方も結構いらっしゃるのではないでしょうか……。
そこで、今回はベートーヴェンやモーツァルト、ショパンのように評価が確立した作曲家たちが残した作品。つまり、「クラシック音楽だけが持つ魅力」と題してお話しできればと思います!
目次
多彩な音域が世界を広げる
間違いなく言えるのはクラシック音楽は、「音域の幅が広い」ということです。
最弱音のピアニッシモから大音量のフォルテ・フォルティッシモまで音質・音色・音量のトーンやレベルは実に多彩で豊富なのです。
曲のイメージを表す調性にしても、嬰へ短調とかニ長調とかト短調とか……、作品の記録には必ずと言っていいほど、その音楽がどのような調で作られているかが記されてあります。
他の音楽ジャンルで、作品にこのような調性がついているのは見たことがありません。
ここで、「音域の幅」について一つの例をあげてみますね。
高音質のヘッドホンでロックやポップスを聴くと大抵は満足できます。それは一定の音量レベルで作られている場合が多いからです。しかし、クラシックの場合だけはそうとも限らないのです。
それは先ほど申し上げたように、作品によって音色や音量、音質が多種多様で何に合わせればいいかという絶対的な基準がないからなのです。
作品の譜面には、「繊細だが豊かな音」「性急だがあわてないように」のような、作曲家の分かったような分からないような? 指示もたくさん書いてあったりします。
ですからライブとCDの録音があまりにも違いすぎるという困った現象も出てきやすいのです。
そのあたりを充分考慮しながら、クラシックをヘッドホンで聴く場合は自分のフィーリングに最も合うものを選ぶべきでしょう。むしろ声楽用、独唱曲用、交響曲用と買い揃えるのも悪くないかもしれません(余裕がある場合ですが……)。
心を揺さぶり、感性を育てる
「感性を刺激する」ことも大きいですね。
「感性」というものは非常にやっかいで、人によって受けとりかたがとてもマチマチなんです。
特にクラシック音楽は聴く人の感性が感動する、しないに大きく関わってくると言えるでしょう。
あわせて読みたい
感性は心のフィルター! 人としての魅力を何倍にもひろげる
感性とは? 皆さん、「感性」という言葉をよく耳にされると思います。 でも今一つ言葉の意味が「わかるような、わからないような……」という方も多いのではないでしょうか…
たとえば交響曲や管弦楽曲の場合は主旋律だけでなく、主旋律を受けとめたり、浮き上がらせる対旋律もしっかりありますよね。これが作品に密度や拡がりを与える大きな要素になるのですが、逆に難しく感じる要素でもあるのです。
また、テンポの変化や間のとり方も独特で、そこから高揚感や悲哀な感情が生み出されたりすることがあります。
最初聴いた時はまったくチンプンカンプンだったけれど、何度も聴くうちに少しずつ良さが伝わるようになってきたというのはよくある話ですね。
それは間違いなく感性が目覚め始めたと言えるでしょう!
クラシック音楽は、一つの音や構成、調性、リズム、テンポなどに様々なメッセージや哲学が込められていますから、聴く人の眠っていた感性を引き出したり、情景が心に浮かんできやすいのです。
「鉄腕アトム」や「ブラックジャック」などの漫画でお馴染みの手塚治虫さんは創作に没頭すると、クラシック音楽を聴きながらイメージを膨らませていたというエピソードもありますが、それもうなづけるような気がします。
あわせて読みたい
クラシック音楽の世界を深める4つの視点
自分の視点が鑑賞を育てる 一般的にクラシック音楽は大作曲家が残した作品や、その演奏を聴いて楽しむことですね。 受け身だと思われがちな音楽鑑賞ですが、場合によっ…
本質的な世界観に共鳴する
クラシック音楽は「波長が高い」とよく言われます。それはなぜなのでしょうか?
中世のグレゴリア聖歌やカトリックのミサ曲、アリア、プロテスタントのカンタータなどは礼拝や祈りを起源としていて、クラシック音楽もその影響下で発展したのでした。
つまりクラシック音楽は少なからずキリスト教の「祈り」や「愛と寛容」の精神が根底にあり、それを受け継いできているのです。
交響曲、協奏曲、独奏曲、室内楽曲、声楽……、どのジャンルも、基本的に人間の本質的な部分に共鳴するように作曲されているので、我知らず高い境地に引き上げられていくことが多いのです。
たとえばバッハの平均律クラヴィーア曲集を聴くと、そのことを実感します。24曲それぞれのプレリュードとフーガは一編の詩や短編小説のように私たちに語りかけ、時には生きることへの問いかけとして心に深く刻まれます。
また、ベートーヴェンは第9交響曲で「苦悩から歓喜へ」というテーマで、運命的な束縛から心身ともに解放される様子をものの見事に表現しています。
彼は「音楽は心から炎を引き出すものでなければならない」と言っております。その言葉どおり、気高い精神と強い情熱は聴く人に無限の勇気や希望を与えてやまないのです。
あわせて読みたい
しなやかで聴きごたえ充分のベートーヴェン! カルロス・クライバー「ベートーヴェン交響曲第7番」
ベートーヴェンの中期の傑作 ベートーヴェンの交響曲はとっつきにくいと思われてます。確かに演奏は難しいし、曲の本質を汲み取るのが大変なのも事実でしょう。 しかし…

![]() 以前からクラシック音楽は「
以前からクラシック音楽は「