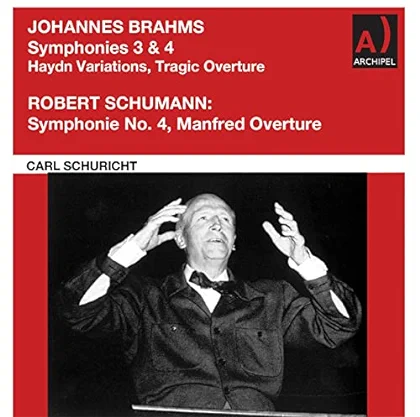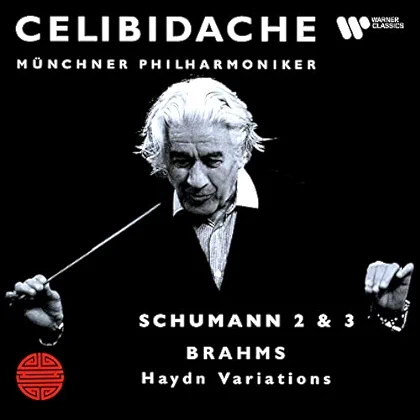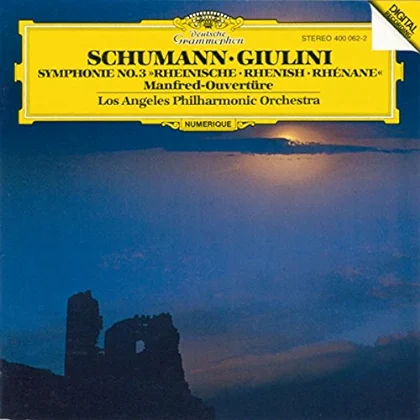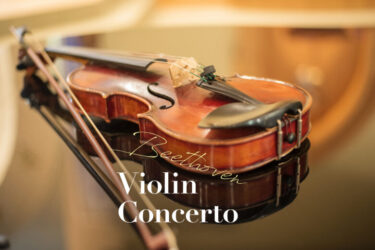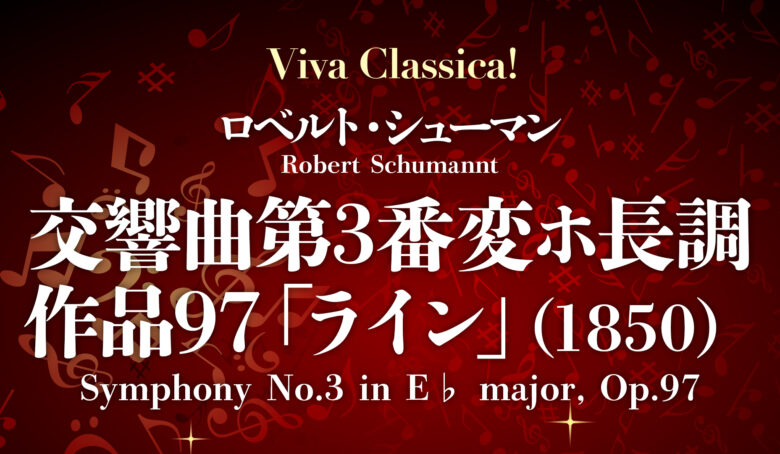
あふれる推進力とロマンチシズム

これは個人的に大好きな曲ですね!
何がいいのかというと、第1楽章最初のテーマから迷わずグイグイ突き進む推進力が最高なのです。しかもまわりくどい序奏がないのも潔くて気持いいですね!
全編に希望と夢が漲っているし、ロマンチシズムの花々が随所に咲き乱れているところもロマン派の大家シューマンらしい……。晩年のシューマンが濃厚なロマンの香りを紡ぎながら、古典的なスタイルに練り上げた交響曲が第3番「ライン」だともいえるでしょう。
1829年にシューマンがお母さん宛に書いた手紙に次のような一文があります。
ライン川はぼくの前に古いドイツの神のようにゆったりと、音も立てず、厳粛に、誇らしげに横たわり、それとともに、山や、谷のすべてがぶどうの楽園である、花が咲き、緑が生い茂る素晴らしいラインガウの全景が広がっていたのです。
シューマンにとってライン川流域の情景は、いつの間にか心の拠り所になっていたことを実感したのかもしれませんね……。
苦境の中で誕生した交響曲

ご存知の方も多いと思いますが、シューマンがこの曲を書き上げた1850年はかなり精神的に不安定な時代でした。そのため人によっては、「病んでる作品」だとか、「全体のバランスが崩れている」とか、「管弦楽がしつこい」とか評価する方も相当数いらっしゃいます。
でも、私は決してそうは思いません。
むしろシューマンは「ライン」を作曲した時、よほどインスピレーションにあふれていて調子が良かったのではないでしょうか……。いや気持ちが乗っていたのかもしれませんね。
その証拠に各楽章に現れる主題の魅力はシューマンらしい歌にあふれていて、美しいロマンチシズムが醸し出されています。
その輝きは創作力の衰えを微塵も感じませんし、聴く者を飽きさせないでしょう。
たとえば第1楽章の毅然としていて格調高い印象的な第1主題、第2主題をはじめとする発展する要素、高まる情感など、曲調と形式が渾然一体となった魅力が充満しているのです!
第2楽章は同じ音型を小刻みに繰り返す主題がゆるやかなラインの流れを想起させます。随所に奏でられるホルンの響きが心のゆとりや風格を伝えてやみません。
中間部の管楽器が奏でる淡く悲しい憂いの表情も後ろ髪を引かれるように過ぎ去っていきます……。
第3楽章はシューマンらしい甘美で無垢なメロディが頻出します。夢と現実の狭間を交錯するようなロマンチシズムの極みが何とも言えません。
作品を決定づけたケルンの旅
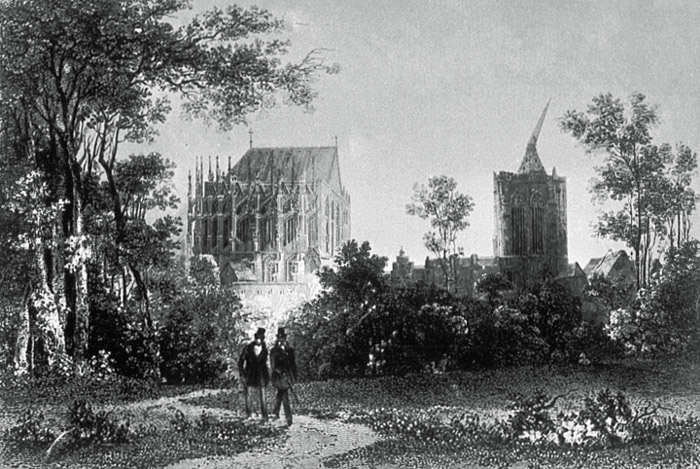


1845年、ドレスデンでの窮屈な生活に疲れはてたシューマンは、妻のクララと7人の子どもたちを連れてデュッセルドルフに引っ越すことになります。
提供されたアパートは決して理想的な空間とは言えなかったようですね。クララによれば、「絶え間ない通りの喧騒、荷馬車の走る音」などが衰弱し、過敏になっているシューマンの神経をさらに追い詰めることになってしまったのでした。
1850年の9月、以前から気になっていたケルンの大聖堂を見るため、クララと共に日帰り旅行に出かけます。
この大聖堂は13世紀に建設されたものの、経済的な理由で未完成のまま工事が頓挫していました。
1842年に、ゴシック様式のブームも後押ししてようやく再建が始まります。1880年に600年の月日を超えてようやく完成しますが、シューマン存命中は遂にその姿を見ることはなかったのでした。
しかし彼はこの大聖堂に佇むうちに、歴史と伝統の重みばかりでなく、途轍もない神聖な雰囲気を感じとっていたのかもしれませんね。
大聖堂から着想を得た第4楽章は、荘厳で崇高な雰囲気の中に、エレジーや鎮魂曲、祈りに似た響きが最高潮に達し、全曲のクライマックスを築いていきます。
このケルンの旅はシューマンにとって、作曲する上での大きな転機となりました。
実際、11月の2度目のケルンの訪問の直前に、第1楽章を完成し、それからわずか1ヶ月半後にはすべてのスケッチとオーケストレーションを書き上げたのです。
聴きどころ
第1楽章・生き生きと
序奏なしで開始される勇壮で堂々とした第1楽章は第1主題からこの曲に惹きつけられる。何という感情の吐露と情熱だろう!
第2楽章・スケルツォ
同じ音型を小刻みに繰り返す主題は悠々と流れるラインを想わせる! ホルンの響きが効果的。中間部の後ろ髪を引かれるような情緒も忘れられない。
第3楽章・速くなく
徹頭徹尾シューマンらしい甘美な夢が音となって鳴り響く。その色彩は曲の進行に伴って陰影を帯びるものの、どこまでも透明で屈託がない。
第4楽章・荘重に
全楽章の最大の聴きどころ。シューマンがケルンの大聖堂から着想を得た管弦楽の結晶度の高い響きが崇高な感動を誘う。
第5楽章・生き生きと
快活でリズミカル。テンポ良く曲は進行し、歓喜のうちにフィナーレを迎える!
YouTube動画
シューマン/交響曲第3番 「ライン」「熊倉優-NHK交響楽団/2023年7月21日 NHKホール
オススメ演奏
カール・シューリヒト指揮・南西ドイツ放送交響楽団
これは凄い演奏ですね! シューマンの心の動き、曲の意味があらゆるパートからグングン伝わってきます。シューリヒトならではの至芸といってもいいし、楽譜の読みの深さなのかもしれません……。
曲の本質をガッチリつかんでいるせいか、テンポが急変したり、加速したりするのに音楽がまったく崩れていないのにはただただ驚きです!
リズムの伸縮や速度も曲調に応じて刻一刻と変化するし、それらがすべて本質を突いているのです。
引き締まった造型に込められた峻烈な歌心、楽器の雄弁な響きなどが一体となって、音楽がたった今生まれるような感動を共有できるでしょう。
セルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団
ステレオ録音で真っ先におすすめしたい演奏はセルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘンフィル(EMI)の演奏です。
相変わらずのスローテンポがチェリビダッケらしいのですが、深い呼吸を伴うダイナミックレンジの広さと細部の彫琢が実に見事です!
音色の立体感や雄大な響きが心地よく、一大シンフォニーとして大河の流れに身を任せるようにこの曲の魅力を味わえるでしょう。
カルロ・マリア・ジュリーニ指揮ロスアンゼルスフィルハーモニー管弦楽団
カルロ・マリア・ジュリーニ指揮ロサンゼルスフィル(ユニバーサル・ミュージック)は、これから「ライン」を聴いてみたい人にとっては最高の名演ですね。
しっかりとした造型と強靭なオケの響きをバックに旋律は良く歌われ、メリハリが効いています。この曲からイメージされるロマン的な情緒をことごとく引き出すことに成功した名演といえるでしょう。
ジュリーニの統率力はオケ全体にも浸透していて、テンポや楽器のバランスが絶妙です。管弦楽のドラマチックな表現や密度の濃さも特筆すべきものがありますね。